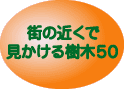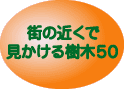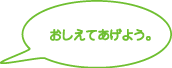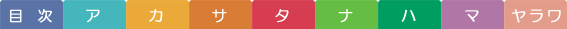 |
 |
 |
 |
 |
|
サザンカ(ツバキ科) |
 |
一般的な特徴
暖地の山地に生える日本特産の常緑小高木(高さ5〜10メートル)です。大きいものは、高さ15メートルにもなります。10〜12月頃
、小枝の先に直径4〜7センチの白い花が咲きます。サザンカは、白、紅、赤、八重咲き、斑入りなどのたくさんの園芸種が作り出
されています。庭木、公園樹、垣根などによく植えられています。秋から冬、初春まで楽しむことができます。ツバキとちがい花
弁は細長く、一枚ずつ分かれて散るのが特徴です。 |
|
分布 四国西南部、九州、沖縄 |
|
|
サツキ(ツツジ科) |
 |
一般的な特徴
川岸の岩場に野生する常緑低木(高さ0.5〜1メートル)です。公園樹、街路樹の下木として用いられ、岩の隙間に植えられてい
ます。4〜5月頃に咲く他のツツジ類より開花時期が遅く、6月頃に花が咲きます。野生種では朱赤色が主ですが、園芸種では白、
赤、絞りなどたくさんの種類があります。 |
|
分布 関東以西の本州、四国、九州、屋久島 |
|
|
サルスベリ(ミソハギ科) |
 |
一般的な特徴
中国南部原産の落葉高木(高さ5〜7メートル)です。江戸時代に渡来しました。中国では百日紅(ヒャクジッコウ)と呼びます。
7月頃、赤い花(または白い花)が開花し、9月頃まで咲き続けます。サルスベリの花は、枝先に円錘花序(えんすいかじょ。花軸
が数回枝分かれし、全体が円錐形をしている花のつき方)をなし、花弁はパーマネント・ウエーブをかけたような縮緬皺(ちりめ
んじわ)があります。サルスベリの名は、樹皮がツルツルで滑らかなことから、サルも滑り落ちるということからついています。 |
|
分布 |
|
|
サンゴジュ(スイカズラ科) |
 |
一般的な特徴
沿岸地の山地に自生する常緑小高木(高さ5〜10メートル)です。古くから「火ぶせの樹」といわれ、防火樹として用いられた。
このほか、庭園樹、公園樹、生け垣としても広く植えられています。葉は、長さ8〜20センチの長楕円形、質は厚く、表面に光沢
がある。6〜7月頃、枝先に大型の円錘花序(えんすいかじょ。花軸が数回枝分かれし、全体が円錐形をしている花のつき方)を
出し、白い花を咲かせます。名は、果実が珊瑚(さんご)の形や色に似ていることからつけられました。 |
|
分布 関東以西の本州、四国、九州、沖縄 |
|
|
シラカシ(ブナ科) |
 |
一般的な特徴
暖地の山地に自生する常緑高木(高さ15〜20メートル)です。雑木林で普通に見られる常緑広葉樹の代表的な木の一つです。
刈り込みに耐えることから、公園樹や垣根によく植えられています。秋には、長さ1.5センチほどの球形または楕円形のドング
リがなります。材質が堅いことから、木炭の材料としても利用されます。名は、材質がカシ類の中で最も白いことからつけられま
した。 |
|
分布 福島県以西の本州、四国、九州 |
|
|
スギ(スギ科) |
 |
一般的な特徴
日本特産で、各地に自生する常緑高木(高さ20〜30メートル)です。建築材、器具材、家具材など有用樹種として、古くから各地
で植林されてきました。日本では、最も長寿の木といわれ、屋久島では樹齢3000年を超えるものがあります。3〜4月頃、スギの梢
(こずえ)から多量の花粉が風に乗って飛散するのが見られます。この花粉が、目や鼻を刺激して花粉症を引き起こす人が多く
なり、アレルギーの人々から嫌われています。名は、まっすぐに伸びるという直木(スクキ)という意味からついたといわれてい
ます。 |
|
分布 本州、四国、九州 |
|
|
ソメイヨシノ(バラ科) |
 |
一般的な特徴
日本の各地で見られる落葉高木(高さ10〜20メートル)です。日本の代表的なサクラとして日本の各地に植えられています。
江戸時代の末期、オオシマザクラとエドヒガンザクラの交配種(こうはいしゅ)として作りだされました。3〜4月頃、葉に先立
って、淡紅色の花を一面に咲かせます。成長が早く、寿命は50年ぐらいで早い時期から古木の風情をかもし出します。名は、江
戸の染井(そめい)の植木屋で作られたことからついています。 |
|
分布 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|