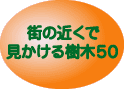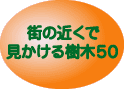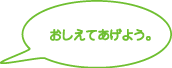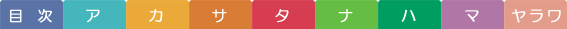 |
 |
 |
 |
 |
|
カツラ(カツラ科) |
 |
一般的な特徴
渓流沿いによく生えている落葉高木(高さ20〜30メートル)です。春の新緑、秋の紅葉ともに美しい木です。大きいものでは、
高さ35メートル、直径2メートルにも達し、一つの株から数本の幹を出します。葉は、ハートの形をしているのでたやすく見分
けることができます。樹の形が優美なことから、街路樹、公園樹などに用いられます。葉は、秋に黄色くなって、落葉するころ
よく匂います。このことから、マッコウノキ、オコウノキ、オコウギなどと呼ぶ地方があります。 |
|
分布 北海道、本州、四国、九州 |
|
|
キンモクセイ(モクセイ科) |
 |
一般的な特徴
中国原産の常緑小高木(高さ3〜6メートル)です。花に芳香があることから庭園樹、公園樹として広く植えられています。大きなも
のは、10メートルを超えるものがあります。東京では、9月下旬に最初のつぼみが開き、少しずれて10月上旬に次のつぼみが咲きま
す。雌雄異株(しゆういしゅ。雌花と雄花が別の株に咲くもの)で、日本にあるのは雄株が多いため果実を見ることはまずありま
せん。 |
|
分布 |
|
|
クスノキ(クスノキ科) |
 |
一般的な特徴
暖地の山地に自生する常緑高木(高さ20〜35メートル)です。日本の照葉(しょうよう)樹林を代表する一つで、古くから、
神社や公園に植えられてきました。大きいものは、高さ55メートル、直径6メートルにも達し、天然記念物になっているものがあ
ります。葉をもむと樟脳(しょうのう)の匂いがします。かつては、幹や根から樟脳を採り、外国に輸出されました。太古には、
タブノキとともに丸木舟の材料として使われました。 |
|
分布 関東南部以西の本州、四国、九州 |
|
|
クヌギ(ブナ科) |
 |
一般的な特徴
山地に生える落葉高木(高さ10〜15メートル)です。樹皮は灰褐色で厚く、縦に深い裂け目ができます。かつては、薪や木炭の材料
として農家の裏山などによく植えられました。今でも雑木林として残り、落ち葉は大切な畑の肥料として、幹はシイタケの原木と
して重宝がられています。夏には、樹液を吸いにカブトムシが集まり、秋には、お椀形の殻斗(かくと)に包まれたドングリがた
くさん実ります。 |
|
分布 本州、四国、九州 |
|
|
クリ(ブナ科) |
 |
一般的な特徴
暖帯や温帯の低い山地に生えている落葉高木(高さ10〜15メートル)です。古代から我が国の重要な食用植物として植栽されてき
ました。縄文時代の遺跡からたくさん出土しています。6〜7月頃、枝の先に淡い黄白色の長い穂をたくさん出し、甘ったるい独特
の匂いを漂わせます。秋になると、鋭いトゲのある殻斗(かくと。イガ)に包まれた堅果(けんか)が実ります。通常、一つの
イガに3個入っています。これを三栗といい、安産のお礼に神社に納めるという風習が地方に残っています。 |
|
分布 北海道南部、本州、四国、九州 |
|
|
クロガネモチ(モチノキ科) |
 |
一般的な特徴
暖地の海岸や山地に自生する常緑高木(高さ10〜20メートル)です。大気汚染に強く、防火性も大きく、また実が美しいことから、
街路樹、公園樹、庭園樹としてよく植えられています。雌雄異株(しゆういしゅ。雌花と雄花が別の株に咲くもの)です。11〜12
月頃、雌株に直径5〜8ミリの球形の実が赤く熟し、華やかな街路樹が現れます。赤い実は、越年し4月頃まで残ります。名は、葉や
枝がモチノキより黒ずんでいることから黒鉄(くろがね)モチとつけられました。 |
|
分布 関東以西の本州、四国、九州、沖縄 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|