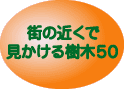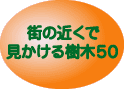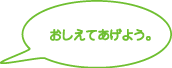|
ケヤキ(ニレ科) |
 |
一般的な特徴
暖帯林、温帯林に生える落葉高木(高さ20〜25メートル)です。日本を代表する広葉樹(こうようじゅ)の一つで、山野に自生
するほか公園樹、街路樹として植えられています。特に関東地方に多く、大きいものでは、高さ50メートル、直径5メートルに達
するものがあり、天然記念物に指定されています。春の芽立ち、夏のみどり、秋の黄葉、冬枯れの木立と、いずれも優れていま
す。また、材が強靱(きょうじん)で、狂いが少なく、木理(もくり)が美しく、長大な柱や板が得られるなど実用性が高い木
です。名は、尊(とおとい)とか秀でたという意味の「けやけき木」からついたといわれています。 |
|
分布 本州、四国、九州 |
|