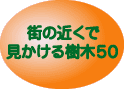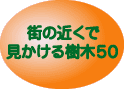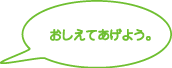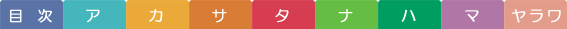 |
 |
 |
 |
 |
|
ナツツバキ(ツバキ科) |
 |
一般的な特徴
山地に自生する落葉小高木(高さ10〜15メートル)です。夏に花をながめ、冬にはまだらな木肌を鑑賞できることから、庭木とし
てよく植えられています。6〜7月頃、白色のツバキに似たきれいな花が、早朝に開花し、夕方にはしぼんで落花します。平家物語
に出てくる「娑羅双樹(しゃらそうじゅ)の花の色」の娑羅双樹の木は、日本ではこのナツツバキが当てられています。 |
|
分布 宮城、新潟県以西の本州、四国、九州 |
|
|
ナナカマド(バラ科) |
 |
一般的な特徴
温帯の山地に自生する落葉高木(高さ10〜15メートル)です。紅葉や実が美しいことから庭木、街路樹などとして植えられていま
す。6〜7月頃、枝先に直径6〜10センチの白い花をたくさん咲かせます。寒地では美しく紅葉し赤い実をつけますが、暖地では花や
実のつきがよくありません。名は、七度竈(かまど)に入れても焼け残るということからつけられました。 |
|
分布 北海道、本州、四国、九州 |
|
|
ナンテン(メギ科) |
 |
一般的な特徴
暖地の山地に生えている常緑低木(高さ2〜3メートル)です。民家の庭先でよく見かけます。5〜6月頃、茎の先に大型の円錘花序
(えんすいかじょ。花軸が数回枝分かれし、全体が円錐形をしている花のつき方)を出し、白い花をたくさんつけます。秋から冬
にかけて、熟した赤い実が見られます。ナンテンは、難転(なんてん)につながるということで、縁起のよいものとされ広く庭
に植えられています。京都の金閣寺にあるナンテンの床柱は、直径6センチもあり有名です。 |
|
分布 茨城県以西の本州、四国、九州 |
|
|
ネムノキ(マメ科) |
 |
一般的な特徴
山野、原野、川岸などに自生する落葉高木(高さ6〜10メートル)です。成長が早く、痩(やせ)地にも育ち、水湿にも強いことか
ら、緑化樹として使われています。7月になると、夕暮れに淡紅色の花が開き始めます。名は、葉を閉じて夜の眠りに入ることから
ついています。長野のネンブリ流し、秋田のネブリ流し、青森のネプタ流しなど、各地の眠り流しの行事を通して、ネムノキは
人々の心にとけ込んでいます。 |
|
分布 本州、四国、九州、沖縄 |
|
|
ノリウツギ(ユキノシタ科) |
 |
一般的な特徴
日当たりのよい山野に生える落葉低木(2〜4メートル)です。7〜8月頃、枝先に白色の両生花(りょうせいか)とその周辺に装飾
花(そうしょくか)をつけます。白色の花弁が紅色に染まったものをベニノリウツギといい、庭園などでよく見かけます。盛夏の
花として知られています。樹皮に粘性の物質を含み、和紙を抄くときのノリとして使います。このため、ニベ、ニベノキ、ノリノ
キ、ネリなどの方言があります。 |
|
分布 北海道、本州、四国、九州 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|