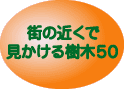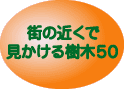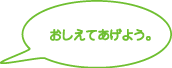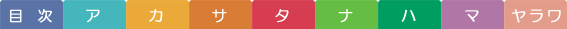 |
 |
 |
 |
 |
|
マテバシイ(ブナ科) |
 |
一般的な特徴
暖帯から亜熱帯に分布する常緑高木(高さ10〜15メートル)です。海岸近くの防潮林、防風林として用いられるほか、工場と道路
の緩衝(かんしょう)緑地帯、公園樹などとして植えられています。葉は、シイ、カシ類の中で最も大きく光沢があります。秋
には、大型のドングリがなり食用になります。名は、実が大味のため「待てば美味しくなる」という意味からつけられたといわれ
ています。 |
|
分布 紀伊半島以西の本州、四国、九州、沖縄 |
|
|
マユミ(ニシキギ科) |
 |
一般的な特徴
山野に自生する落葉小低木(高さ3〜5メートル)です。紅葉や実が美しいことから、庭木、公園樹としてよく植えられています。
雌雄異株(しゆういしゅ。雌花と雄花が別の株に咲くもの)です。秋、淡紅色に熟した実が裂け、赤い種子が現れます。名は、弾
力があって堅い材が弓に向く、真弓(まゆみ)からつけられたといわれています。 |
|
分布 北海道、本州、四国、九州 |
|
|
マンリョウ(ヤブコウジ科) |
 |
一般的な特徴
暖地の常緑樹林下に自生する常緑低木(高さ0.5〜1メートル)です。鑑賞用として広く栽培されます。秋から冬にかけて美しい赤
い実(まれに白)が熟します。小鳥によって運ばれた実が発芽したものがしばしば見られます。マンリョウは、万両(まんりょう
)に通じ、縁起ものとして鉢物として正月に飾られます。同じ時期に出回るセンリョウは、これとはまったく別のセンリョウ科の
植物です。 |
|
分布 関東以西の本州、四国、九州、沖縄 |
|
|
ムクゲ(アオイ科) |
 |
一般的な特徴
中国原産の落葉低木(高さ1〜2メートル)です。花が美しいことから、生け垣などによく植えられています。韓国名ではムクン
ゴアナムと呼ばれ、美しい白色の花は国花になっています。花は、朝開いて夕方にはしぼんで落ちてしまう一日花です。このこ
とから、謹花一朝(きんかいっちょう)の夢などともいわれています(白楽天の詩)。白花のつぼみは、食用や薬用になり、樹
皮からは丈夫な繊維や紙に利用できることから、昔から家の近くによく植えられていました。 |
|
分布 |
|
|
モッコク(ツバキ科) |
 |
一般的な特徴
海岸に近い山地に自生している常緑高木(高さ10〜15メートル)です。潮風、大気汚染に強いことから、環境緑地帯、庭園樹、
公園樹として植えられています。果実は、直径1.5センチの球形で秋になると赤く熟くします。材も赤みを帯び、緻密(ちみつ)、
堅牢(けんこう)であることから、床柱、細工物として重宝されています。琉球では首里城(しゅりじょう)の建築材として使わ
れています。 |
|
分布 千葉県以西の本州、四国、九州、沖縄 |
|
|
モミ(マツ科) |
 |
一般的な特徴
丘陵や低山に普通に生えている日本特有の常緑高木(高さ20〜30メートル)です。大きいものは、高さ40メートル、直径2メートル
にも達します。同じ仲間が、朝鮮半島、中国大陸に分布しています。大気汚染に弱く、大都市や工業地帯では、被害にあい残り少
なくなっています。モミといえば、クリスマスツリーを思い浮かべますが、多くはドイツトウヒを使います。 |
|
分布 秋田県以西の本州、四国、九州、屋久島 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|