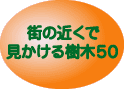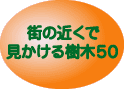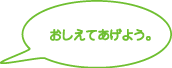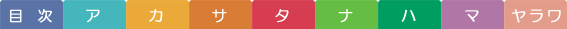 |
 |
 |
 |
 |
|
アオキ(ミズキ科) |
 |
一般的な特徴
暖かい地方の林の中に普通に生えている常緑低木(高さ1〜2メートル)です。一年中青々とした光沢のある葉と赤く熟した果実が
美しいことから、庭木としてよく植えられます。葉にまだらや星の模様が入っている園芸品種もあります。雌雄異株(しゆうい
しゅ。雌花と雄花が別の株に咲くもの)です。12月頃、雌木にナツメの実に似た赤い実がなります。名は、幹(みき)が青いこ
とからついています。 |
|
分布 宮城県以西の本州、四国、九州、沖縄 |
|
|
アカマツ(マツ科) |
 |
一般的な特徴
山野にごく普通に見られる常緑高木(高さ30〜35メートル)です。乾燥に強く、尾根筋や痩せ地にもよく育つことから、
植林されてきました。大きいものでは、高さ50メートル、直径2.5メートルにも達します。樹皮は赤褐色で、幹の下部が暗褐色
になり、老木になると亀の甲羅(こうら)状に裂けます。材には、たくさんの松ヤニを含むことから、古くから日本家屋の梁材、
土木用材などとして利用されてきました。1950年代頃から、太平洋岸を中心にマツクイムシの被害が広がり、アカマツ林の純林が
少なくなっています。 |
|
分布 北海道西南部、本州、四国、九州 |
|
|
アジサイ(ユキノシタ科) |
 |
一般的な特徴
暖地の海岸沿いに自生しているガクアジサイを改良した落葉低木(高さ1〜2メートル)です。欧米で改良して逆輸入したものを
セイヨウアジサイといい、白、桃、紅、赤、青などの花色や、矮性(わいせい)で花が咲く鉢物があります。最近では、各地に
アジサイの新名所ができていますが、ほとんどはセイヨウアジサイで占められています。梅雨どきには、やはり本来のアジサイ
がよく似合います。憂愁(ゆうしゅう)の花をひっそり眺めるのに適しています。 |
|
分布 房総半島、三浦半島、伊豆諸島、足摺岬 |
|
|
アセビ(ツツジ科) |
 |
一般的な特徴
暖地に生育する常緑性の低木(高さ1〜2メートル)です。箱根、伊豆には大きな株のものがあります。春浅い雑木林の中で、
小さいつぼ形の花の穂をたくさん垂れ下げているのが見られます。遠くからみると、ふっくらとした白い花は、たくさんのご
飯粒が緑の葉の上にのっているように見えます。東北地方ではコメノキ、中国地方ではムギメシバナとも呼んでいます。アセ
ビの名は、万葉集で馬酔木(あしび)と詠まれ、馬がこの葉をたべると中毒して足がしびれ動けなくなることからつけられたと
いわれています。 |
|
分布 山形県以西の本州、四国、九州 |
|
|
アベリア(スイカズラ科) |
 |
一般的な特徴
中国原産の常緑低木(高さ0.5〜1.5メートル)です。大正末期に渡来しました。よく分岐して茂ることから、公園樹、庭園樹、
道路の分岐帯などによく植えられています。花の後ろが衝羽根(つくばね)状なので、ハナゾノツクバネウツギという別名があ
ります。夏から秋まで、小枝の先に可愛い花が咲き続けます。花は、白粉(おしろい)の匂いがします。 |
|
分布 |
|
|
イチイ(イチイ科) |
 |
一般的な特徴
深山に自生する常緑高木(高さ10〜15メートル)です。日陰地でもよく育ち、刈り込みにも耐えることから、庭園樹、公園樹、
生け垣、盆栽などとして用いられています。別名、オンコ、オララギとも呼ばれています。9〜10月頃、果実が赤く熟します。
旧一万円札の聖徳太子が掲げている笏(しゃく)は、このイチイから作られました。 |
|
分布 北海道、本州、四国、九州 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|