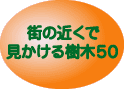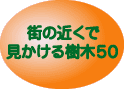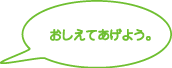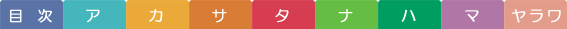 |
 |
 |
 |
 |
|
イチョウ(イチョウ科) |
 |
一般的な特徴
中国原産の落葉高木(高さ20〜30メートル)です。室町時代に渡来しました。世界各地で植裁され、公園や社寺の境内には大きな
木が見られます。大きいものでは、高さ45メートル、直径5メートルに達するものがあります。樹木としては、地球上で現存する
最も古い種で、生きている化石といわれています。雌雄異株(しゆういしゅ。雌花と雄花が別の株に咲くもの)で、雌株には実
がたくさんなり銀杏(ぎんなん)として食べられます。 |
|
分布 |
|
|
イヌマキ(マキ科) |
 |
一般的な特徴
暖地の山地に自生する常緑高木(高さ15〜20メートル)です。大きいものは、高さ25メートル、直径2メートルにも達するものが
あります。雌(めす)木と雄(おす)木が別々の木で、雌木には赤紫色の肉質のある花托の上に、緑色した球形の果実をつけます。
名は、昔マキと呼んだスギに比べて劣るという意味がイヌマキとつけられました。 |
|
分布 関東南部以西の本州、四国、九州、沖縄 |
|
|
イロハモミジ(カエデ科) |
 |
一般的な特徴
低い山地の普通に生えている落葉高木(高さ15〜20メートル)です。大きいものは、30メートルにも達するものがあります。紅
葉が美しいことから、庭園樹、公園樹としてよく植えられています。モミジは、本来は秋に草木が黄色や赤色に変わること意味
する言葉です。転じて、目立って色が変わるカエデの仲間をモミジと呼ぶようになりました。果実は、翼(つばさ)を持った二
分果(にぶんか)がプロペラ型になっています。 |
|
分布 福島県以西の本州、四国、九州 |
|
|
エゴノキ(エゴノキ科) |
 |
一般的な特徴
山地に自生する落葉高木(高さ10〜15メートル)です。雑木林にクヌギやコナラなどとともに普通に生えています。5月下旬、
新緑の葉に埋めつくされた中に、枝一面に純白色の花を下向きに咲かせます。雨の日など、歩道を埋めるように落ちている白
い花に気づいて、思わず立ち止まって仰ぎ見ます。かつては、果皮にエゴサポニンを含んでいることから、石けんの代わりに
使いました。 |
|
分布 北海道、本州、四国、九州、沖縄 |
|
|
エノキ(ニレ科) |
 |
一般的な特徴
山地に生える落葉高木(高さ15〜20メートル)です。環境保全樹、公園樹として植えられています。大きいものは、高さ25メート
ル、直径1.5メートルにも達するものがあります。樹皮は厚く、灰黒褐色で斑点がありざらざらしています。10月頃、小さなやや
球形の実が赤褐色に熟します。果実は甘く小鳥が好んで食べます。昔は、街道の一里塚として植えられました。 |
|
分布 本州、四国、九州 |
|
|
オオムラサキ(ツツジ科) |
 |
一般的な特徴
原産地不明の園芸種で常緑低木(高さ1〜2メートル)です。ヒラドツツジの品種群の一つといわれています。根付きがよく
、排気ガスにも強いことから、街路樹の下木としてよく見られます。また、樹の形を整えやすいことから、庭木、庭園樹とし
ても植えられています。4〜5月頃、枝先に大きな赤紫色の花が2〜4個群がって咲きます。 |
|
分布 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|